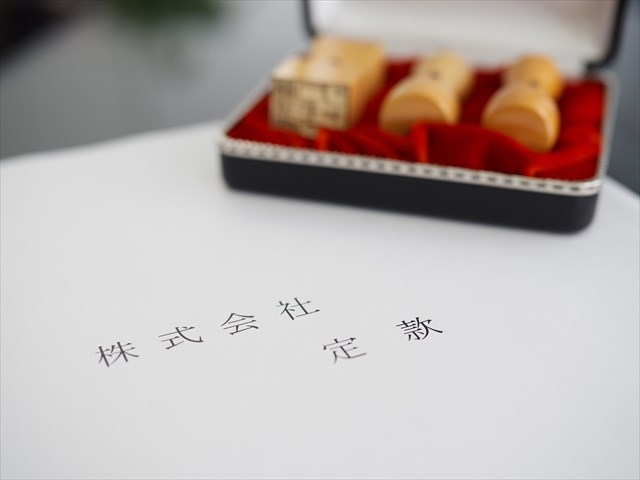どんな会社であっても設立時に定款を欠かすことはできません。さらに、株式会社においてはその定款について「認証」の手続も行わなければなりません。
ここではこの認証の手続について解説します。
定款の認証は何のために行うのか
「認証」では、定款の中身がチェックされます。
定款の内容が法令に反したものになっていないかどうか、会社設立をするのに必要な要件をクリアできているかどうかを評価されるのです。
定款が適式に作成されていないと会社設立が無効になることもありますので、会社設立手続のうち「定款作成」はとても重要な意味を持っているのです。
とりわけ株式会社においては会社経営者である取締役、会社所有者である株主が登場するなど、比較的複雑な権利関係が生じます。そこで定款が有効に成立したことをチェックする過程を設ける必要性が特に高いのです。
※株式会社にのみこの認証手続が求められている。
※合同会社や合資会社、合名会社などでも定款は必要ですあるが、認証を受ける必要はない。
認証手続は公証役場で行う
定款の認証は、公証役場で行います。そこで、認証を受けようとする日より前にアポを取っておくようにしましょう。
また、その間に必要書類の準備も進めておきましょう。少なくとも「定款の原本」が3通必要です。会社で保存するだけでなく公証役場でも1通保存することになりますし、その後設立登記を行うときにも認証を受けた謄本を1通用意しなくてはならないためです。
ほかに、発起人の印鑑登録証明書も必要です。
認証費用
定款の認証を受けるには費用がかかります。金額は3万円から5万円で、資本金額に応じて決定されます。
資本金額が100万円に満たないときは「3万円」、100万円を超えて300万円に満たないときは「4万円」、その他の場合は「5万円」です。
なお、紙ベースで定款を作成したときは収入印紙の貼付も必要です。4万円分の印紙税を納めることになります。
ただし電子定款も認められており、このとき印紙税は非課税です。少しでもコストを下げたい場合は電子定款を作成すると良いでしょう。
定めた期日に公証人へ見せる
日程調整して決めた期日にて、公証役場へ行きます。そして公証人と呼ばれる方に定款を見せて認証を求めます。
不備があると修正を加えるなどの手間が発生しますので、心配のある方は事前に弁護士や司法書士、行政書士などの専門家にチェックしてもらった方が良いです。
公証人も法律のプロですので、適当に作成してごまかすことはできません。